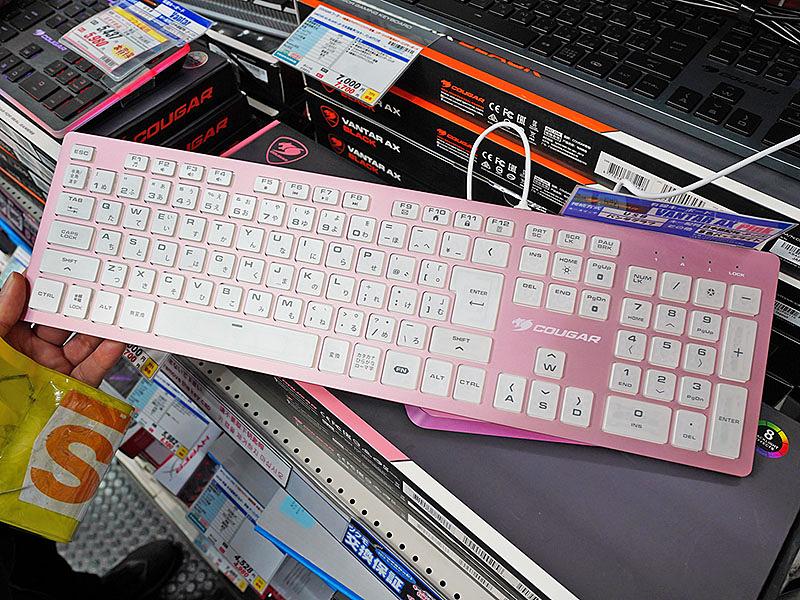ブルー・ラブ・ビーツ、UKジャズ新世代が明かす生演奏×ビートメイクの新たな可能性
ブルー・ラブ・ビーツ(Blue Lab Beats、以下BLB)はUKジャズ・シーンでよく知られた存在だが、その文脈のなかにどう位置付けるべきなのか悩ましい存在だった。2018年の1stアルバム『Xover』には多くのジャズ・ミュージシャンが参加しているが、サウンドの中心にあるのは生演奏ではなくプログラミングされたビート。ジャズのエッセンスは多少含まれている程度で、どちらかといえばローファイ・ヒップホップ、もしくはチル系ビートメイカーみたいな印象を抱いていた。
しかしその後、プロデューサー/ビートメイカーの「NK-OK」ことナマリ・クワテンと、マルチ奏者の「Mr DM」ことデヴィッド・ムラクポルによるデュオのイメージは、少しずつ変化していくことになる。2019年の次作『Voyage』ではオーガニックなサウンドを手に入れ、生演奏を引き立てるプロデュースの手腕に、彼らがジャズのコミュニティに属している影響がはっきり実感できるようになった。
ブルー・ラブ・ビーツのプロデュース/ビートメイク担当、「NK-OK」ことナマリ・クワテン
ブルー・ラブ・ビーツの生楽器担当、「Mr DM」ことデヴィッド・ムラクポル
そこからBLBの背景を辿っていくうちに、Mr DMは様々な作品に起用されているUKジャズ・シーンのキーマンのひとりであることを知った。彼はシーンの顔役である鍵盤奏者、ジョー・アーモン・ジョーンズの作品に欠かせないベーシストとしてハイブリッドなサウンドに貢献しながら、トランペット奏者のマーク・カヴューマ率いるオーセンティックなジャズ・バンドではヴィブラフォンを叩くという、文字どおりマルチな才人だった。もう一方のNK-OKも、「ドラム・マシーン奏者」として様々なセッションに参加している。この2人はプロデューサー・チームであると同時に、2人の優れたプレイヤーによるユニットでもあった。
彼らはスタジオ・パフォーマンス動画をいくつもアップしているが、そのうちの多くでMr DMのキーボード/ベースとNK-OKのドラム・マシーンによる生演奏がフィーチャーされている。こうしたプレイヤーとしての側面と、プロデューサーとしての資質を組み合わせる方法論こそが、BLBがシーンで高く評価されてきた要因なのだろう。そして彼らは、作品を重ねながら方法論に見合うだけのスキルを習得し、自分たちのサウンドを徐々に完成させていった。
そういった強みをもつからこそ、BLBはアフリカの要素を取り入れるとなれば、プレイヤーとしてのアフロビート(フェラ・クティ文脈)と、プロデューサーとしてのアフロビーツ(ウィズキッドに象徴される今日的なダンスミュージック)の両方に取り組み、横断することができる。さらに、地元のジャズ・ミュージシャンからアフリカのラッパーまで、様々なゲストとのコラボでも相乗効果を生み出せる。そういった彼らの個性はアフリカを代表するシンガー、アンジェリーク・キジョーをも魅了。彼女の2021年作『Mother Nature』ではプロデュースも手掛けている。
昨年にはジャズの名門ブルーノートと契約。同年のEP『We Will Rise』を経て、最新アルバム『Motherland Journey』ではこれまで以上に生演奏とプログラミングの融合が進み、飛躍的な成長ぶりを見せている。ゲストの顔ぶれも多彩で、ガーナで知り合ったゲットー・ボーイ、キル・ビーツのようなアフリカのアーティストから、キーファーなどアメリカ勢までコラボしており、UKの枠組みを超え始めている。
そんなBLBのバックグラウンドについては意外にも情報が少ない。なので、彼らの音楽的な背景をじっくりと聞き出すことにした。彼らとUKジャズ・シーンとの繋がりもしっかり語ってもらっている。このふたりを受け入れる懐の広さが、このシーンが活況を呈している理由でもあるのだろう。
BLMの学生時代、音楽的ルーツ
―まず、ふたりが出会ったWac Arts Collegeについて教えてください。
Mr DM:1978年にCelia Greenwoodがロンドンに設立した学校で、コートニー・パイン、スティーヴ・ウィリアムソン、ジュリアン・ジョセフ、ミス・ダイナマイトら著名人を多数を輩出している。音楽でも歌もあれば作曲もある。映像もダンスもあって、いろんなアートに興味のある人たちがファミリーみたいに学べる雰囲気がある場所だね。
NK-OK:アートを学ぶ場所はかなり高額な学費が必要になることが多い。でも、Wac Arts Collegeでは音楽に限らず、映像や演劇などを安い学費で学ぶことができる。通常なら2時間で40〜60ポンドはかかるレッスンがたった2ポンド。ここは歴史のある学校なんだけど、ずっと授業料を変えていないんだ。僕らはここで学んでいる頃に出会った。当時、ランチ・ホールでビートを作っていたら、デヴィッド(Mr DM)が「何やってんの?」って話しかけてきて、そこで意気投合して、一緒に演奏するようになったんだよね。
Mr DM:僕はライブ・ミュージックをやっていたんだけど、ここで印象深かったのは譜面を使わずに耳で聴いて覚える授業。耳で覚えてから、みんなで一緒に演奏をするんだ。そうやってすごくオーガニックなやり方で音楽を学ぶことができたと思う。
NK-OK:僕はミュージック・プロダクション。いろんなクラスがあって、ドラマ、ダンス、舞台演出とかいろんなものが学べる。いろんな人がいろんなことを学んでいる状況が一か所に集まっているというのは、常に何かしらのインスピレーションがあるということだから。
Wac Arts Collegeの紹介映像
―Mr DMはその後、ミドルセックス大学へ進学し、ジャズを学んでいます。
Mr DM:大学ではしっかり譜面を学ぶことにフォーカスしていったと思う。ジャズのスタンダードをかなり勉強したし、作曲に関しても深く学んだ。ホーン・プレイヤーを加えた編成のために曲を書いたりもしたし、ビバップ、ハードバップ、モーダルジャズ、様々なスタイルの曲を書いたのは良かったと思う。
オーセンティックなジャズ・トリオで、ピアノを演奏するMr DM
―Mr DMはマルチプレイヤーですが、そもそも大学の頃のメインの楽器は?
Mr DM:1年目はエレクトリック・ベース。2年目がヴィブラフォン。3年目以降はいろんな楽器に手を出した。大学の外ではそういった様々な楽器を使ってギグをやっていたよ。
―ヴィブラフォンだったら打楽器科のドラマーが並行して演奏したりとか、ベースとギターなら同じ弦楽器だから弾きやすいとか、複数の楽器をやる場合はやりやすい組み合わせがあると思うんですけど、Mr DMの場合はバラバラだったんですね。
Mr DM:大学で選んだ楽器の前に、僕は3歳の時、最初の楽器としてドラムを始めて、その後にキーボードを弾くようになった。そこからエレクトリック・ベースをやって、ヴィブラフォンを選んだ。だから自然な選択だよね。
この投稿をInstagramで見るDavid Mrakpor(@davidmrakpor)がシェアした投稿Mr DMとジェイコブ・コリアー。ふたりは2005年、同じロンドン・ミルヒルの高校に通っていた。
―その頃、NK-OKはどんな活動をしていたのでしょう。
NK-OK:僕は15歳の時にはすでに(レーベルと)契約していたからね。最初に通ってた学校はあまりいい学校じゃなくて途中で行かなくなったんだけど、父のクワメ・クワテンがミュージシャンだったので(アシッドジャズの名ユニット、D・インフルエンスのメンバー)、 11歳のころからホームスクーリングで音楽を学ぶことができた。
最初は「eJay Hip Hop 5」ってアプリをダウンロードしたんだけど、トライアル版だったから20点くらいしかサンプルが入ってなくて、それを切ったり貼ったりしまくってなんとかトラックを作っていた。僕のエディットの基盤はそこで身についたものだね。その後でGarageBandを使うようになり、Logicにも手を出したという流れ。そんなことを2年やってて、高校に進学する年になって、GCSE(中等教育修了証明書)を取得するくらいの頃に、父親から「この先も音楽をやって食っていきたいんだったら、それができることを自分で証明しなさい」って言われてね。それでトラックを作って、契約を勝ち取って、ミュージシャンになったという感じ。
ちなみに今、ビートを作るのに使っているのはNative Instruments社のMASCHINE MK3のオレンジ・エディション。ライブのときはAbletonを使っているけど、これはまだ発展途上って感じ。ビートを作るときはLogicを使ってる。
この投稿をInstagramで見るNK-OK(@nkok.productions)がシェアした投稿(左)2011年、ビートメイクを始めた頃のNK-OK (右)2015年、BLBがパブリック・エネミーのサポートを務めた際のNK-OK
―NK-OKが影響を受けたプロデューサーについて教えてください。
NK-OK:ヒップホップでいうと、まず最初に挙げるべきはピート・ロック。DJプレミアからも同じくらい影響を受けている。あとはミッシー・エリオット。彼女はアーティストとしてはもちろんだし、プロデューサーとしても素晴らしい才能を持っていた。後者については過小評価されていると思う。ティンバランドとのコンビが有名だけど、むしろティンバランドの良さを引き出したのがミッシーじゃないかって僕は考えているくらい。
それから、パトリース・ラッシェン。ヴォーカリストやキーボード奏者としての彼女についてはよく知られているけど、コンポーザーとしての側面ももっと知られていいと思う。彼女の作曲面からの影響は大きいね。あとはもちろん、クインシー・ジョーンズも。実は以前、バックステージで会って話をさせてもらう機会があった。あれは信じられない経験だったね。
―今挙がったのはアメリカ人ばかりでしたが、イギリスの音楽に関してはどうですか?
NK-OK:もちろん影響を受けている。ヒップホップにのめり込む前、僕はグライムに夢中だったからね。音楽業界に入るきっかけを作ってくれたのはグライムだったと言える。Kano、Ghettsなど、本当にたくさんのUKラップ・ミュージックを聴いていた。だから、自分のなかにグライムを始めとしたUKサウンドの影響が大きくあるのは間違いない。
―Mr DMはどんな演奏家や作曲家から影響を受けてきたんですか?

Mr DM:自分に最も大きな影響を与えたのは、1982年にパトリース・ラッシェンがリリースした『Straight From The Heart』。これが不動のナンバーワン。特に収録曲の「Forget Me Not」は僕にとってのベスト。ウィル・スミスの映画『メン・イン・ブラック』でサンプリングされているのでずっと前から聴いていたけど、元ネタがパトリース・ラッシェンと知って聞き返したら、あまりにすばらしくて一瞬で魅了された。それにオスカー・ピーターソン。『Piano Moods』(ベスト盤)で好きになって、そこからいろいろ聴いたら『Night Train』がベストだなって思った。そのふたりがトップ2だね。
あとは、16歳の頃にラジオから流れてきたドン・ブラックマンにも一瞬でぶっ飛ばされた。そして、バーナード・ライトが1981年にリリースした『Nard』。彼が16歳の時にプロデュースしたアルバムで、誰もあんなの作れないと思う。信じられない作品だね。
ガーナで受けた衝撃、フェラ・クティとウィズキッドからの学び
―Mr DMに質問で、ジョー・アーモン・ジョーンズやマーク・カヴューマとはどんなきっかけで知り合ったんですか。
Mr DM:マークとは2013年にTomorrows Warriorsを介して知り合った。毎週日曜にTomorrows Warriorsが企画していたジャム・セッションがNoliasというヴェニューであって、そこで初めて会ったんだ。マークはトランぺッターのShane Forbes、サックス奏者のRuben Foxといった偉大な先輩ミュージシャンとも交流していた。僕らは意気投合して、そこから一緒にギグをやるようになった。彼の2作目『Bang Factory』のタイトルは彼が率いるコレクティヴの名前を冠しているんだけど、僕はその一員としてヴィブラフォンを演奏している。
マークとの関係で言えば、最近、『Legacy』というアルバムをリリースしたキネティカ・ブロコ(Kinetika Bloco:ロンドンで活動するマーチングバンド。アフリカ、カリブ、ジャズ、ラップなど様々な音楽文化を若者に伝えている)にも触れないといけない。キネティカ・ブロコとTomorrows Warriorsはかなり近い関係なんだ。キネティカ・ブロコはMat Foxが2000年ごろに創設した団体で、今は彼の息子が引き継いでいる。マークを介して僕はここでも演奏するようになって、その縁で『Legacy』へも参加することになった。
Mr DMが参加した、マーク・カヴューマ率いるBang Factoryのライブ映像
キネティカ・ブロコ『Legacy』のティーザー映像。上述のマーク・カヴュ―マやRuben Foxに加えて、ヌバイア・ガルシアやテオン・クロスといったUKジャズの重要人物も参加。
Mr DM:ジョー・アーモン・ジョーンズに関しては、2013年頃に彼が参加していたジャズ・ヒップホップ・コレクティヴのセッションで知り合った。彼らは毎週木曜にブリクストンでセッションをやっていて、そこではミュージシャンだけではなく、ラッパーが来てサイファーをやったりもしていた。僕はそこのジャムによく参加していたんだ。そこから意気投合して、彼のアルバム『Starting Today』と『Turn To Clear View』で4曲ずつ演奏している。それにBLBの作品にも彼は参加してくれている。
NK-OK:僕もそのブリクストンのセッションにはよく行っていた。僕はドラム・マシーンを持っていったんだけど、最初は生演奏の場所だし、ロウな感じが好まれていたからなかなかドラム・マシーンで参加することを理解してもらえなかった。だから、あまり演奏する機会をもらえなかったんだけど、徐々に変わっていって、途中からは「またドラム・マシーンを持ってきてくれよ」って感じで声をかけらえるようになった。僕にとって大切な経験だね。
Mr DMがベースで参加した、ジョー・アーモン・ジョーンズ『Turn To Clear View』収録曲「Try Walk With Me」
―BLBにとって大切なコンセプトなんですか?
NK-OK:コラボレーションは自分たちにとって大きな要素、そこではなるべくトラックのデータを送りたくないというのがこだわりかな。一緒にスタジオに入って、同じ部屋で一緒に演奏することが大事なんだ。それによってお互いの音楽制作のプロセスもわかるし、そこで上手くコネクトしていくと、何をやっても呼吸や歩調を合わせられるようになる。
―ライブ感を大事にしている。
NK-OK:そう。データのやり取りだけで曲を作るのはできるだけ避けたい。ロックダウンの時は仕方ないからリモート制作もやったけど、極力スタジオで一緒にやるようにしている。
―その辺は意識的なんですね。『Xover』の頃から器楽奏者やヴォーカリストを迎えていたり、オーガニックなセッションっぽさがある気がしていたので。
NK-OK:僕らはBLBを名乗る前、いろんなヴォーカリストのプロデュースをやっていた時期があって、そのためのトラックをひたすら作っていた。その時に僕らの楽器のソロを入れるってアイデアが浮かんだから試しにやってみたら、すごくいい感じだったんだ。それ以来、生演奏を積極的に入れていくように変わっていった。そこが今思えば、BLBが始まった瞬間だったと思う。
そこから自分たちの音楽をやるようになって、色んなヴェニューで他のアーティストたちと交流したりするうちに、ロンドンには自分たちと似たフィーリングを持つミュージシャンが相当いることに気づいた。だったら、僕らの作品に呼んで一緒に演奏したらよさそうだなって。そのアイデアが『Xover』に繋がっていった。あれはコラボを推し進めることで完成したアルバムで、改めて振り返ってみると、あの頃にいろんなアーティストとコラボしながら僕たちの音楽が徐々に固まっていったと思う。そうやって積極的にコラボを続けてきた結果が今のBLBだね。
―『Xover』の時点でジャズやヒップホップ、ネオソウル、ブギー、アフロビート、カリビアンミュージックなどいろんな要素が入っていました。多様なサウンドを一枚にまとめることもコンセプトとしてあったんですか?
NK-OK:そこが自分たちのシグニチャーだと思ってる。BLBのコンセプトの土台になっているのは、スティーヴィー・ワンダーの『Songs in The Key of Life』。あのアルバムはいろんなジャンルの音楽が入り混じっている。しかも、信じられないクオリティだよね。あの時代はあらゆるジャンルの音楽家たちが、自分の作品のなかにいろんなジャンルを取り入れるチャレンジをしていたと思う。だから、僕らもいろんなジャンルを渡り歩くような実験をしたい。それに、BLBはまだまだ発展途上だから、様々なジャンルを出入りすることで自分たちの音楽的なボキャブラリーを広げていきたいって思いもあるね。
―今回のアルバム『Motherland Journey』はアフリカやカリブのルーツを意識したサウンドが印象的です。ここではアフリカン・ディアスポラみたいなコンセプトもあったのかなと想像しますが。
NK-OK:まさにそうだね、タイトルにもそれが反映されている。以前、ガーナにMVを撮影しに行ったとき、オフの時間でクラビングをしていた。その時にすごく衝撃的だったのが、ガーナのクラブにいろんなジャンルを組み合わせてかけるDJがいたこと。まさに自分たちがこれまでにやってきたこと、自分たちのめざすコンセプトそのものが、クラブのセッティングで行われていて。あれには本当に驚いたな。サウンドシステムも素晴らしかったし、ベースの鳴りも尋常じゃなかった。それに何より、様々なジャンルがどんどんミックスされていく感覚が、アフリカ系の人たちが歩んできたジャーニーを思い起こさせるようなものでもあった。僕らが(自分たちのルーツでもある)西アフリカに戻ってきたことを深く実感し、自分たちの腰が(音楽に合わせて)自然と低くなるような経験だった。そして、あのときクラブで体験した音楽に比べたら、自分たちの音楽はまだまだミックスの仕方が甘いんじゃないかって思うようになったんだ。
―もともとBLBの音楽にはアフロビーツの要素もあったし、NK-OKはサックス奏者Kaidiとのコラボで『The Sounds of Afrotronica』というアルバムも発表していたり、アフリカの音楽と熱心に取り組んできた印象です。
NK-OK:最初に西アフリカの要素を取り入れてみたのは、モーゼス・ボイドやヌバイア・ガルシアも参加した「Pineapple」という曲(『Xover』収録)。当時、アフリカ的なサウンドをもつ曲はこれだけで、「ファンからの反応がいい曲だな」くらいに思っていたけど、気づいたらBLBにとって最大の人気曲になっていた。
その後、アフロビーツにも意識的に取り組むようになり、だったら現地の素晴らしいアーティストにも声をかけることにして、ゲットーボーイやキルビーツが参加することになった。しかも今回は、フェラ・クティのアカペラまで(音素材として)使えることになった。この許諾が下りたときは驚いたよね。「ぜひ使ってくれ」とメールの返事が来てから3カ月間、どうすべきか悩んで音源に手が付けられなかったくらい。そうやってシーンに足を踏み入れていくと、もっと実験的なことをやりたいと思うようになるし、そういうチャレンジも楽しかった。アフロビーツにはシンプルさがあって、そのシンプルさゆえの難しさが最も大きな挑戦だったと思う。
フェラ・クティのアカペラを使ったタイトル曲「Motherland Journey」
―『Mother land Journey』を作る際、影響を受けたアーティストは?
NK-OK:近年はWizkidの『Made in Lagos』を聴きまくっていた。このアルバムはアフロビーツのドラム・プログラミングのお手本みたいなサウンドだから。初めて聴いたときはぶっ飛ばされたよね。
―ドラム・マシーンと言えば、このアルバムではドラマーがセッションしているようなビートに驚きました。正直、ドラマーなのかプログラミングなのか聴き分けられないくらい。そして、Mr DMもこれまで以上にソロをたくさん弾いてますよね。今までの作品と比べて、ライブ感が突出しているように思いました。
NK-OK:いろんな人から「本当はドラムセットを叩いているんじゃないか?」って言われるんだけど、実際はすべてプログラミングなんだ。僕はスネアドラムの音作りだけでも2時間かけて作り込む。ドラムをヒットする一つ一つの音を強弱を変えたりしながら、その一音一音にふさわしいニュアンスで打ち込んでいく。なるべくリアルなドラム・ビートにしたいからね。そもそも僕の楽器に関する経歴を話すと、最初はジャンベから始めたんだ。その後にドラムセットに行って、そこからプロダクションへと移行した。でも、ずっとプロダクションをやってきたら、今度はドラムが恋しくなってきた。だから、ドラム・マシーンをサンプラーとしてではなく、楽器として使うことを思いついた。それが僕のビートの特徴になっていると思う。
この投稿をInstagramで見るNK-OK(@nkok.productions)がシェアした投稿
Mr DM:今回、ライブっぽい音作りにしたのはロックダウンの影響もある。あの時期のロンドンでは、閉塞感に耐えられなくなった人たちが公園で息抜きをしていた。そこでは楽器を奏でている人たちが大勢いて、演奏を聞きつけたミュージシャンが次第に集まりだして、自然発生的にジャム・セッションが生まれていた。もちろんソーシャルディスタンスを保ちながらね。僕らも公園で演奏したし、誰かが演奏している光景を眺めていたこともあった。そこでの素晴らしい体験が、今回のアルバムの方向性を決めたんだ。
この投稿をInstagramで見るNK-OK(@nkok.productions)がシェアした投稿
ブルー・ラブ・ビーツ
『Motherland Journey』
発売中
詳細:https://Blue-Lab-Beats.lnk.to/Motherland_JourneyPR